イボとは
イボとは、皮膚に数ミリから数センチほどの隆起がみられる病変で、その状態や性質はさまざまです。一般的な皮膚疾患の一つであり、原因としてウイルス感染や加齢などが挙げられます。
イボは外見上の問題となるだけでなく、かゆみや炎症などの症状を伴うこともあります。また、衣類に引っかかって日常生活に支障をきたすこともあります。放置するとサイズが大きくなることもあり、進行すると綺麗に治すことが難しくなる場合があります。
主なイボの種類
イボ(尋常性疣贅:じんじょうせいゆうぜい)
尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)は、イボの中でも代表的な種類です。このイボは、ヒトパピローマウイルス(HPV)が皮膚の傷口から感染することで発症し、その性質から「ウイルス性疣贅」とも呼ばれます。
尋常性疣贅は通常、痛みやかゆみを伴いませんが、放置すると増加したり他人に感染する可能性があるため、注意が必要です。幅広い年齢層で見られますが、特に学童期のお子さんに多く発生する傾向があります。
発生部位によって形状はさまざまで、手足の指や膝に現れる場合は硬くて表面がざらざらした状態になることが多いです。足の裏など圧力がかかる場所では平たくなり、顔や首では細長い糸状の突起として現れることがあります。さらに、複数のイボが融合し、敷石状になるケースもあります。
尋常性疣贅を放置すると、サイズが大きくなるだけでなく、掻いたり触ったりすることでウイルスが拡散する可能性があるため、早めの対策が重要です。
水イボ(伝染性軟属腫:でんせんせいなんぞくしゅ)
水イボは、伝染性軟属腫(でんせんせいなんぞくしゅ)ウイルスである「ポックスウイルス」に感染することで発生するイボです。主に6歳以下の子どもに多くみられ、特に夏場に発生しやすいのが特徴です。水イボは、以下のような皮膚の薄い部分や擦れやすい部分によくみられます。
- 胸
- お腹
- 脇の下
サイズは数ミリ以下のものが多く、形状は小さな光沢のあるドーム状です。かゆみを伴うこともあり、掻くことで内容物が皮膚に付着し、さらに広がる可能性があります。また、イボのサイズが大きくなると炎症を起こしやすくなります。
水イボは自然治癒が期待できる一方で、完治までに数カ月から1年以上かかることもあります。その間に全身に広がったり、他の子どもへの感染源になったりする恐れもあります。直接接触だけでなく、プールでのタオルや浮輪、ビート板などの共用品を介して感染するため、集団生活を送る子どもでは注意が必要です。こうした感染を予防するためには共用品の使用を避け、感染した場合は早期に治療を受けることが大切です。
老人性イボ(脂漏性角化症:しろうせいかくかしょう)
老人性イボは「脂漏性角化症」とも呼ばれ、紫外線による肌の加齢性変化が原因とされる良性の皮膚腫瘍です。中年以降に多く見られますが、20代でも発症例は少なくありません。
老人性イボは以下の部位に発生しやすく、茶色や黒っぽい茶色の盛り上がりで、類円形の腫瘤として現れることが特徴です。
- 顔面
- 頭部
- 胸元
表面はざらざらとしたイボ状の感触で、大きさはさまざまです。
老人性イボは日光性のシミ(老人性色素斑)から発生することが多いです。悪性化はしませんが、皮膚がんとの区別が難しい場合があり、鑑別診断が必要になることもあります。また、数カ月以内に全身に多発したり、かゆみを伴ったりする場合は、内臓悪性腫瘍との合併(レザー・トレラ徴候)の可能性があるため、精密検査が必要です。
保険適用がある治療には、手術による切除が挙げられます。
首イボ(アクロコルドン)
イボにはさまざまな種類がありますが、大きく分けてウイルス感染性(尋常性疣贅・伝染性軟属腫)と非感染性(老人性イボ)に分類されます。非感染性である老人性イボ(脂漏性角化症)が首や脇の下、鼠径部など皮膚が薄い部分に生じると、有茎性に盛り上がった小さなイボとして現れます。これを首イボ(アクロコルドン)と呼び、主な原因として皮膚の老化や紫外線、摩擦などが考えられています。
首イボは良性腫瘍のため、健康上の深刻な問題を引き起こすことはありませんが、衣類との摩擦で痛みや炎症が生じる場合があります。また、加齢に伴い数が増加し、襟の開いた服を着た時に目立ったり、ネックレスが引っかかることで不快感を覚える方もいます。
首イボの治療法としては、主に特殊なハサミを用いた切除法が行われます。イボの数が少なければ当日に処置が完了しますが、多数ある場合は1~2週間の間隔を空け、複数回に分けて治療を行います。
イボの治療
イボの治療法は、サイズや数、年齢などによって大きく異なります。当院では、患者様それぞれの状況に適した治療法を検討し、ご提案しています。イボが気になる方は、お気軽にご相談ください。
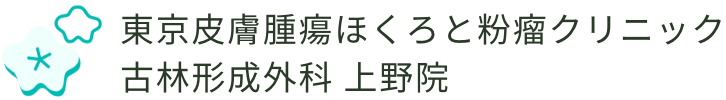

 アクセス
アクセス


