粉瘤が化膿して腫れたらどうする?原因・治療法・応急処置まで徹底解説

「粉瘤が腫れて痛い」「膿が出てきた」「破裂してしまった」——そんなときはすぐに医師の処置が必要です。
化膿した粉瘤は、放置しても自然に治らず、悪化すると強い痛み・発熱・跡が残ることもあります。
この記事では、
- 粉瘤がどうして化膿するのか
- 自宅でできる応急処置とNG行為
- 病院で行う治療の流れ(切開排膿〜袋ごとの切除)
- 再発を防ぐためのポイント
を詳しく解説します。
「破裂してしまったけど大丈夫?」「市販薬で治せる?」と悩んでいる方は、このページで今すぐやるべきことが分かります。
粉瘤が化膿してしまう原因
細菌感染による炎症
粉瘤(アテローム)は、皮膚の下に袋(嚢腫)ができ、その中に皮脂や角質がたまる良性腫瘍です。通常は袋の中に内容物が入っているため炎症もなく、違和感があっても基本的には痛みを伴いません。しかし外的刺激などで袋が破れると内容物に黄色ブドウ球菌などの細菌が繁殖し化膿して赤く腫れ上がります。
どの部位に粉瘤ができても感染が起こる可能性はありますが、特に首・背中・耳の後ろ・お尻など、汗や皮脂が多く通気性の悪い部位や擦れや圧のかかる部位では感染が起こりやすくなります。
自己処置や圧出による悪化
「中の膿を出したい」「早く治したい」と自己判断で潰すと、袋が破裂して内部に細菌が広がり、急速に炎症が悪化することがあります。袋を取り出さないと治らないため、無理に押し出したり針で刺したりするのは周囲との癒着も起こり、今後の治療が難しくなるため厳禁です。
不衛生な環境・免疫低下も影響
睡眠不足やストレスなどで免疫力が低下していると、細菌感染を起こしやすくなります。皮膚を清潔に保ち、炎症のサイン(赤み・熱感・痛み)を感じたら一気に痛みが発生し悪化します。
炎症が起きている場合は根治手術ができず、切開排膿と言って一旦起きた炎症を逃すことしかできません。炎症が起きてない時に根治手術を行う事が唯一の治療法となります。
化膿した粉瘤の治療方法
切開排膿
化膿した粉瘤では、まず袋の中に溜まった膿を外に出す処置(切開排膿)が行われます。根治手術にはならず、一旦援助を抑えるための治療となります。
局所麻酔をして小さく切開し、内部を洗浄して感染を鎮めます。腫れや痛みは数日で落ち着きますが、この段階では袋自体は残っているため、後日再発することがあります。
抗生剤による炎症のコントロール
切開後や軽度の炎症の場合には、抗生物質の内服や塗り薬で炎症を抑えます。市販の軟膏ではなく、医師が症状に応じて処方する抗生剤(セフェム系・ニューキノロン系など)を使用します。
こちらも起きた炎症を抑えるための治療なので、根治手術にはなりません。炎症が収まってから数カ月経って袋ごと取る根治手術を行います。
再発防止のための袋ごとの切除手術
炎症が落ち着いた後、再発を防ぐためには袋ごと摘出する「根治手術」が必要です。
手術は局所麻酔で日帰り可能。袋を完全に取り除くことで再発を防ぎます。形成外科では傷跡が目立たないように切開ラインを工夫し、美容的な配慮も行われます。
化膿した粉瘤は何科で診てもらうべきか
皮膚科
軽度の炎症や初期の診断・抗生剤処方は皮膚科で対応可能です。炎症が強い場合や再発を繰り返す場合は、形成外科や外科への紹介になることがあります。
形成外科
切開排膿を繰り返しても再発したり、大きな範囲の炎症で膿が大量に溜まっている場合はを形成外科が最適です。
炎症管理を行い袋の除去をきっちり行う事で再発を防ぎます。同時に縫合技術に優れており、美容面にも配慮した治療が受けられます。
外科
膿が広範囲に広がり、深部組織まで波及している場合や感染が重度で全身管理を伴うなどの場合には、市中病院や大学病院など大きめの施設の救急や外科に治療を任せる事があります。
化膿した粉瘤に関するQ&A
化膿していた粉瘤が潰れて破裂してしまいました。熱を持っています。冷やすなど病院に行く前にどのような処置をすればいいですか?
潰れた部分は清潔なガーゼで覆い、冷やして炎症を抑えるのが応急処置として有効です。市販の軟膏を塗るよりも、まずは感染の拡大を防ぐことが大切です。早めに病院を受診し、適切な排膿と抗生剤治療を受けてください。
粉瘤が化膿を繰り返しています。放置したら今後どうなりますか?
繰り返し炎症を起こすと、皮膚が硬く変形し、膿瘍や瘢痕(はんこん)化を起こします。袋を取る手術をしないと根治にならないため、最終的に大きな手術が必要になることもあります。
粉瘤の化膿を止めるために市販薬(リンデロン、ゲンタシン、ドルマイコーチ、ロキソニンなど)は効きますか?
リンデロン(ステロイド)は炎症を抑えますが、感染がある粉瘤には悪化させてしまうため不向きです。ゲンタシンなどの抗生物質軟膏は軽度なら補助的に使えますが、ドルマイコーチは抗生物質に加えステロイドも入った混合薬のため感染のリスクが上がります。ロキソニンは痛みや熱を抑える対症療法として一時的に使用可能です。
化膿した粉瘤の切開排膿を他院で受けましたが、再発しました。再手術は可能ですか?
はい、可能です。炎症がおさまった後に袋ごと切除すれば、再発リスクを大幅に減らせます。他院で再発した粉瘤の再手術にも対応できます。
化膿した粉瘤の局所麻酔が痛いと言われますが、なぜ化膿すると麻酔が効きにくいのですか?
化膿した組織は酸性に傾いており、アルカリ性の局所麻酔薬が中和されて作用しにくくなると言われています。また炎症している部分は血流が増加しているため、局所麻酔薬が注射されてもすぐに流れ去ってしまうのも理由となります。
皮膚科では粉瘤と言われたできものが、肛門科では膿皮症と言われました。違いは何ですか?
粉瘤は袋の中に皮脂が溜まる良性腫瘍、膿皮症は毛穴や汗腺に細菌が感染して化膿する炎症性疾患です。見た目が似ているため混同されることがありますが、原因も治療法も異なります。
化膿した粉瘤がある状態で温泉やプールに入ると悪化しますか?
はい、悪化する恐れがあります。温泉やプールでは細菌感染のリスクが高まり、化膿部分からさらに炎症が広がることがあります。完治するまでは入浴やプールは控えましょう。
まとめ
- 粉瘤が化膿する主な原因は細菌感染や自己処置による悪化
- 化膿した場合は切開排膿で膿を出し、炎症が治まったら袋ごと切除するのが根治法
- 市販薬では根本的に治らず、放置すると再発や変形を起こす
- 形成外科での治療が最も安全で再発予防に効果的
- 応急処置は清潔・冷却が基本、早期の受診を
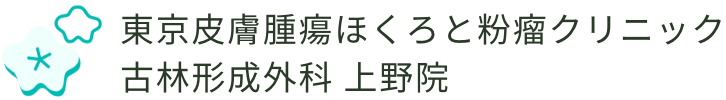

 アクセス
アクセス


