赤いほくろは大丈夫?悪性腫瘍(メラノーマ・基底細胞癌)との違いと見分け方
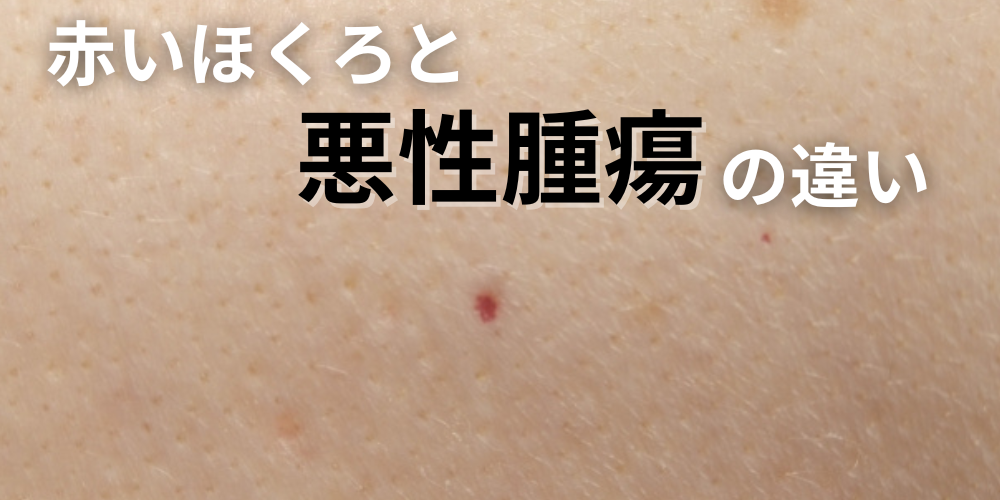
赤いほくろは多くの場合「老人性血管腫」などの良性の血管性腫瘍ですが、まれに悪性腫瘍(メラノーマや基底細胞癌)と見た目が似ていることがあります。
色や形の変化、痛みや出血などがある場合は自己判断せず、医療機関での診断が重要です。
この記事では、赤いほくろと悪性腫瘍の違いや見分け方、診療科の選び方、悪性の場合の検査方法まで、形成外科クリニックの視点から解説します。
「これって本当にほくろ?」と少しでも不安を感じた方は、ぜひ参考にしてください。
赤いほくろと悪性腫瘍(メラノーマ・基底細胞癌)の違いと見分け方
赤いほくろは多くの場合「老人性血管腫(Cherry angioma)」という良性の血管性腫瘍です。加齢や紫外線、遺伝的要因などによって、30代以降に増える傾向があります。
しかし、赤色や赤黒色の皮疹の中には、まれに悪性腫瘍(メラノーマや基底細胞癌)が含まれることがあり、見た目だけで自己判断するのは危険です。
色の違い
- 赤いほくろ(老人性血管腫):均一な鮮紅色や暗赤色。色むらはほとんどなし。
- メラノーマ:黒や濃い茶色が基本だが、赤みや白色、青色が混ざることも。色の境界が不規則になりやすい。
- 基底細胞癌:黒~褐色、または光沢のあるピンク色。中央がやや陥没することもある。
形・輪郭の違い
- 良性は円形で境界が明瞭。
- 悪性は輪郭がギザギザ、にじむように広がる、不規則な形をとることがある。
大きさの変化
- 良性の赤いほくろは数mm程度で安定している。
- 悪性は数週間~数カ月で拡大することが多く、5mmを超える場合は要注意。
痛みや出血の有無
- 良性は基本的に無症状。
- 悪性は出血、かさぶた、しこり感、潰瘍化、痛みやかゆみなどを伴うことがある。
赤いほくろではなく癌かも?診療科・クリニックの選び方
皮膚科を選ぶケース
炎症や急な変化がない場合は、まず皮膚科で診察を受け、必要に応じて精密検査や専門医への紹介を受けるのも一つの方法です。
皮膚科では視診や拡大して皮膚を観察できる「ダーモスコピー」を用いた鑑別が行われます。
形成外科を選ぶメリット(仕上がり+病理検査対応)
首や顔など見た目が気になる部位を、確実に診断したい場合、形成外科が最適です。
形成外科は外科的切除や縫合に熟練しており 、
- 傷跡を首のシワや輪郭に沿わせるデザイン
- 目立ちにくい縫合法(真皮縫合・細かい表皮縫合)
が可能です。
さらにここで切除した組織は病理検査に回し、顕微鏡で細かく組織を見ることで悪性の有無を判断し、確定診断が可能です。
これにより「見た目も安心も確保したい」という希望を同時に満たせます。
悪性腫瘍(メラノーマ・基底細胞癌)だった場合の検査方法
ダーモスコピー検査
特殊な拡大鏡で皮膚表面の色素パターンや血管構造を観察し、良性・悪性の特徴を見分けます。
非侵襲的で痛みはなく、外来で数分で行えます。
皮膚生検(病理検査)
局所麻酔をして病変の一部または全てを切除し、顕微鏡で細胞の状態を観察します。
- メラノーマの場合:腫瘍の厚さや深達度を測定し、進行度を判定。
- 基底細胞癌の場合:腫瘍の広がりや組織型を確認し、再発リスクを評価。
これらの結果に基づき、追加切除や放射線治療などの方針が決まります。
Q&A
赤いほくろから年齢とともに悪性化することはありますか?
老人性血管腫は悪性化しません。ただし、もともと悪性腫瘍が赤い斑点として始まる場合もあるため、変化があれば早めの受診が必要です。
赤いほくろが掻いたり刺激を与えたりして悪性化することはありますか?
刺激で直接悪性化することはありませんが、繰り返しの出血や炎症で見た目が変わり、悪性腫瘍との判別が難しくなることがあります。
ほくろが出来た場所によって診療科を変えた方がいいですか?
- 顔や首:仕上がり重視なら形成外科
- 背中や腕:診断優先なら皮膚科でも対応可能
ただし、悪性の疑いが強い場合は部位に関わらず病理検査ができる医療機関を選びましょう。
まとめ
赤いほくろの多くは良性ですが、メラノーマや基底細胞癌など悪性腫瘍との区別は見た目だけでは困難です。
色・形・大きさの変化、出血や痛みがある場合は早期受診が必須です。
特に首や顔など目立つ部位では、
- 悪性の有無を確実に確認
- 傷跡を目立たせない縫合
- 必要に応じた追加治療へのスムーズな移行
が可能な形成外科での診察をおすすめします。
「大丈夫だろう」と放置せず、少しでも不安を感じたら早めに医療機関で確認しましょう。
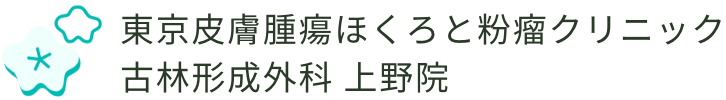

 アクセス
アクセス


