眼瞼下垂の症状
私たちは、1日に約2万回、年間では約700万回のまばたきをするとされています。加齢とともに足腰が衰えるように、まぶた(眼瞼)の機能も徐々に低下します。腱膜性眼瞼下垂症は、主に加齢による衰えが原因で発生し、長生きすれば誰にでも起こる可能性があります。
まぶたの機能低下は徐々に進行するため、気づきにくいのが特徴です。まぶたが下がるだけでなく、さまざまな症状が現れますが、これらを眼瞼下垂と認識できないと、自覚するのが難しい場合があります。
眼瞼下垂症の主な症状|当てはまる症状はありませんか?
上まぶたが重く感じて、目が開けにくい
視野が狭くなってきた
まわりの人から眠たそうだと言われることが増えた
目を開けるときに眉毛が吊り上がったり、おでこに深いシワができたりする
何かを凝視するときに自然に顎が上がる
肩こりや頭痛、首の痛みが慢性的に起こる
眼精疲労がひどい
まぶたの上にくぼみができた
二重(ふたえ)の幅がはっきりとしてきた
右目と左目の開き具合に違いがある
初期段階では、上まぶたが重く感じられ、目を開けにくくなることで周囲から「眠そう」と言われたり、視野が狭くなったりすることがあります。
症状が進行すると、視界を確保するために頭を後ろに傾けたり、顎を上げるような姿勢をとるようになります。また、まぶたを開ける力が弱くなることで、前頭筋(ぜんとうきん)を使い眉毛とまぶたを持ち上げようとするため、額に太い横シワが目立つようになります。
眼瞼下垂の随伴症状
眼瞼下垂では、まぶたが垂れ下がるだけでなく、随伴症状として肩こりや首こり、緊張性頭痛が生じることがあります。これらの症状は、額の筋肉の緊張が持続することによって引き起こされるため、眼瞼下垂に伴う症状として珍しくありません。
まぶたの筋肉には神経受容体が存在し、これは周囲の変化を脳に伝えるセンサーの役割を果たしています。眼瞼下垂症によって腱膜がゆるむと、神経受容体が刺激され、その信号が脳や中枢神経に伝わります。その結果、体内の神経バランスが乱れ、さまざまな症状が引き起こされることがあります。
めまい
不眠症
不安障害
自律神経失調症
眼瞼や表情筋の痙攣
眼瞼下垂の原因
まぶたの上げ下げの動作には、動眼神経が支配する上眼瞼挙筋(じょうがんけんきょきん)と、交感神経系が支配するミュラー筋(別名:瞼板筋)の2種類の筋肉が関与しています。これらの筋肉が協調して働き、瞼板を引き上げることで、まぶたが開きます。
筋肉と瞼板は腱膜という組織で繋がっています。この腱膜が緩むと、筋肉の力が瞼板に十分に伝わらず、まぶたの挙上が困難となります。眼瞼下垂の多くは、この現象によって引き起こされるとされています。また、皮膚のたるみや筋力の低下も眼瞼下垂の要因となります。
眼瞼下垂には、大きく分けて「先天性眼瞼下垂」と「後天性眼瞼下垂」の2種類があります。先天性眼瞼下垂は、生まれつきまぶたが下がっている状態を指し、後天性眼瞼下垂は、正常だったまぶたが次第に下がってくる状態を指します。後天性の場合、主に加齢が原因とされていますが、長期間のハードコンタクトレンズの使用や白内障手術などの既往歴がある場合も発生リスクが高まります。
先天性眼瞼下垂
先天性眼瞼下垂とは、生まれた直後から見られる眼瞼下垂のことを指します。まぶたを持ち上げる上眼瞼挙筋の形成不全や、筋肉を動かすための神経の発達異常が主な原因とされています。先天性眼瞼下垂には片側性と両側性があり、片側性が全体の約8割を占めます。
眼瞼下垂によって視界が下方に制限されるため、顔を後ろに傾けたり、眉毛を上げて目を開けたりする姿勢を取る必要があります。症状が重い場合には、視力にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
また、まれに交感神経に関係する疾患であるホルネル症候群が原因で眼瞼下垂が現れるケースもあります。ホルネル症候群は、眼球と脳を結ぶ神経経路の障害によって引き起こされる疾患で、まぶたの下垂以外にも以下の症状が見られることがあります。
ホルネル症候群には、先天性のものと後天性のものがあります。
ハードコンタクトレンズの長期使用
ハードコンタクトレンズの長期使用が眼瞼下垂を引き起こすことがあります。特にソフトレンズよりもハードレンズを使用している方に多く見られ、ハードレンズを10年以上使用している場合は、高確率で眼瞼下垂を発症するとされています。
人は1日15,000〜20,000回程度まばたきをするとされています。ハードレンズを装着した状態で長期間まばたきを繰り返すことで、上まぶたを支えているミュラー筋や挙筋腱膜の収縮力が低下し、それが眼瞼下垂の原因となります。
さらに、レンズの取り外し時にまぶたを強く引っ張る習慣も、眼瞼下垂を引き起こす要因となります。コンタクトレンズが原因の眼瞼下垂は、片側のまぶたにのみ現れやすいのが特徴であり、その結果、目の左右差が目立つことに悩む方も少なくありません。
加齢
加齢とともに身体機能が低下するのと同様に、まぶたの機能も年齢を重ねるにつれて徐々に衰えます。
まぶたの機能を維持するには、「腱膜」と「瞼板」という組織が重要な役割を果たしています。これらの組織がしっかりと結びつくことで、挙筋の力が効率的に伝わり、まぶたをスムーズに上げることができます。
しかし、加齢によって腱膜と瞼板の結合がゆるんだり、挙筋腱膜自体が弱くなったりすることで、まぶたを上げる力が十分に伝わらなくなります。さらに、腱膜と瞼板の結合が完全に外れてしまうと、挙筋の力ではまぶたを上げることができなくなります。このような状態を「腱膜性眼瞼下垂」と呼び、主に加齢が原因で引き起こされます。
また、加齢による皮膚のたるみも、まぶたの動きを妨げる原因の一つです。
内眼手術の既往
眼瞼下垂は、以下のような眼科手術を受けた場合に生じることがあります。
これらの手術中に使用される「開瞼器(かいけんき)」という器具が原因とされています。この器具は、まぶたを強制的に開かせるために使用されます。しかし、開瞼器を長時間使用すると、眼瞼挙筋や腱膜に負担がかかり、その結果として眼瞼下垂が発生することがあります。
神経麻痺・筋肉の疾患
まれなケースですが、神経麻痺や筋肉の疾患が原因で眼瞼下垂を引き起こすこともあります。以下のような疾患が原因として挙げられます。
脳動脈瘤や糖尿病による動眼神経麻痺
肺がんなどによる交感神経麻痺
重症筋無力症(神経と筋肉の接合部に異常が生じる疾患)
これらの疾患では、眼瞼下垂以外にもさまざまな症状が現れることがあります。その場合、眼瞼下垂の治療よりも、これらの疾患に対する治療が優先されることが一般的です。
眼瞼下垂の手術
眼瞼下垂の手術の種類は、主に以下のとおりです。
挙筋前転術(きょきんぜんてんじゅつ)
挙筋短縮術(きょきんたんしゅくじゅつ)
眼瞼皮膚切除術(がんけんひふせつじょじゅつ)
前頭筋吊り上げ術(ぜんとうきんつりあげじゅつ)
患者様の眼瞼下垂の状態にあわせて、これらの中から適切な手術方法が選択されます。
挙筋前転術(または挙筋短縮術)
挙筋前転術(または挙筋短縮術)は、衰えた挙筋腱膜を縮めることで、まぶたを引き上げる手術です。
この手術は、上眼瞼挙筋と瞼板の間にある腱膜が伸びている場合に主に行われます。挙筋短縮術では、伸びた腱膜を瞼板から剥離し、一部を短く切除した後、再び瞼板に縫い付ける方法が採用されます。
これにより、たるんだ腱膜が修復され、上眼瞼挙筋の力が瞼板に効率的に伝わるようになり、まぶたが開きやすくなります。また、まぶたの皮膚にたるみがある場合には、同時に皮膚切除術を併用することもあります。
眼瞼皮膚切除術
眼瞼皮膚切除術とは、皮膚のたるみが生じた際に行われる手術で、たるんだ皮膚を切除することでまぶたの下垂を改善する方法です。まぶたを上げるために必要な上眼瞼挙筋や腱膜が正常に機能している場合でも、皮膚のたるみによって下垂が生じることがあります。このような場合に、この手術が適用されます。
眼瞼皮膚切除術には、二重形成を目的として皮膚を切除する方法や、たるんだ皮膚を眉毛の下で切除する「眉下切開」などの方法があります。
前頭筋吊り上げ術
前頭筋吊り上げ術とは、上眼瞼挙筋腱膜が著しく機能低下し、挙筋前転術では改善が見込めない眼瞼下垂に対して行われる手術です。この手術では、前頭筋(おでこの筋肉)の力を利用してまぶたを引き上げるのが特徴です。
まず、眉毛上部とまつ毛上部を切開し、まぶたの皮下に紐を通します。紐には、通常、ふとももから採取した筋膜を加工したものを使用します。紐で前頭筋とまぶたを連結することで、眉毛の動きがまぶたに伝わり、まぶたの開閉がスムーズになります。
保険適用による眼瞼下垂手術
当院では、保険診療による眼瞼下垂手術を行っています。美容目的の手術は実施しておらず、治療対象はまぶたの下垂によって視力低下や視野狭窄などの機能的な障害が生じている患者様です。
保険適用の対象となる症状は、主に以下の通りです。
まぶたが下がって視界が狭くなる
上方や側方が見にくい
まぶたが垂れてくるため、手で持ち上げる
おでこや頭に力が入り、頭痛や肩こりが続いている
まつ毛が視界に入ったり、まつ毛が目の中に入ったりする
眼瞼下垂の手術内容や症状について気になる点がありましたら、お気軽にご相談ください。
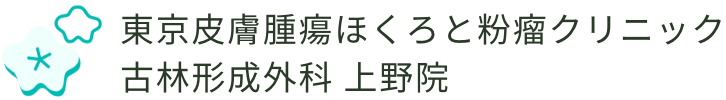

 アクセス
アクセス









