皮膚がんとは
皮膚がんとは、皮膚に発生する悪性腫瘍を総称したものです。皮膚がんの手術治療は、形成外科領域の手技の一つに含まれています。皮膚がんにはさまざまな種類があり、主に以下のものが挙げられます。
- 基底細胞がん
- 有棘細胞がん(扁平表皮がん)
- 悪性黒色腫(メラノーマ)
これらのがんは、おとなしい性質のものから悪性度の高いものまで多岐にわたります。
内臓のがんとは異なり、皮膚がんは目視で確認できるため、早期に発見しやすいのが特徴です。そのため、皮膚がんの疑いがある症状や、医療機関を受診すべきタイミングについての知識を持つことが重要です。
ここでは、主な皮膚がんの種類、良性・悪性の見分け方、一般的な治療法について解説します。
良性・悪性の見分け方
皮膚がんの種類は以下のように、さまざまな特徴があります。
- イボのような隆起したもの
- シミのような隆起のないもの
- 湿疹のように赤く腫れているもの
- ほくろに似ているもの
良性か悪性かを判断する指標として、硬さや表面の状態などがあげられます。
硬さ
悪性腫瘍の場合、表面にでこぼこがあり、硬い感触のものが多いのが特徴です。周囲の組織と癒着していることもあり、その場合は押してもあまり動きません。
一方で、良性腫瘍は柔らかく、なめらかな表面のものが多いです。腫瘍の内容物は周囲の組織から独立しているため、押すとコリコリと動きます。
表面
悪性腫瘍の場合、表面が出血している、ジクジクしている、周囲との境界が不明瞭、かさぶたがあるなどの特徴があります。ただし、このような特徴がない悪性腫瘍も存在します。
完全に見極める方法は?
良性か悪性かを完全に見極めるには、医学的な診断が必要です。自己判断は避け、専門医による診察を必ず受けましょう。
皮膚がんの治療では、基本的に外科的切除が行われます。皮膚がんが疑われる際には、ダーモスコピーという特殊な拡大鏡を用いた検査や、転移の可能性がある場合には超音波やCT、MRIなどの画像検査が実施されることもあります。また、確定診断のために腫瘍の一部を採取し、病理検査を行うケースもあります。
これらの検査は、適切な治療方針を決めるために重要ですが、必ずしもすべての検査を行うわけではありません。
多くの方は、できものができただけではすぐに医療機関を受診しないかもしれません。そこで、次に医療機関を受診する判断材料として、皮膚がんの特徴をご紹介します。
代表的な皮膚がんの種類と特徴
皮膚には、外気と接する最外層の表皮と、下層の真皮があります。表皮は外部からの異物侵入を防ぐバリアとして機能しています。また、古くなると垢となって剥がれ落ち、新しい表皮が形成されます。
下層の真皮には血管、リンパ管、神経が豊富に存在し、体の感覚や栄養補給に重要な役割を果たしています。真皮のさらに下には皮下脂肪、筋肉、骨と続いています。
皮膚がんは、真皮にはほとんど発生せず、主に表皮の有棘細胞や基底細胞ががん化することで発生します。また、色素細胞(ほくろのもとになる細胞)ががん化したものが悪性黒色腫(メラノーマ)であり、「ほくろのがん」とも呼ばれます。
皮膚がんの代表的な種類には、これらの「表皮細胞がん」と「悪性黒色腫」が含まれます。
基底細胞がん
基底細胞がんは、日本人に最も多くみられる皮膚がんです。表皮の最も深い層である基底層や、毛を包み込んでいる毛包の細胞から発生すると考えられています。高齢者の頭部や顔面(頬、まぶた、鼻、口の周り)に発生しやすい傾向があります。
基底細胞がんは黒や灰色をしており、ほくろに似た外見で、表面に光沢のある小さな隆起として現れます。年数を経るごとに徐々に大きくなり、進行すると中心部がくぼんで潰瘍を形成し、周囲が盛り上がる独特の形状になります。通常、痛みやかゆみといった自覚症状はありません。
基底細胞がんは一般的にリンパ節や他の臓器への転移はまれですが、適切な治療を受けずに放置すると、周囲の健康な組織を破壊しながら成長し、深部の筋肉や骨にまで浸潤する可能性があります。特に、皮下脂肪の薄い顔面では深部への浸潤が起こりやすく、骨組織に影響を与えることもあります。
治療の主な方法は外科的切除です。ただし、完全に除去しないと局所再発のリスクがあるため、初回の手術で確実に取り除くことが重要です。基底細胞がんの主な原因は紫外線(日光)によるものであるため、予防には紫外線対策が効果的です。
有棘細胞がん(扁平上皮がん)
有棘細胞がん(扁平上皮がん)は、基底細胞がんに次いで日本人に多く発生する皮膚がんです。このがんは、表皮の有棘層の細胞が悪性化することで発生します。隆起したしこりのような形状をしているため、イボと勘違いされることも珍しくありません。高齢者に多くみられ、頭皮や顔(鼻、耳、唇、まぶた)、手の甲などに好発します。また、やけどや傷あと(瘢痕)のある部位にも発症することがあります。
有棘細胞がんの原因には、日光(紫外線)の暴露や、子宮頸がんの発生要因でもあるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が挙げられます。さらに、放射線治療後の慢性皮膚炎や日光角化症、Bowen病(ボーエン)などの前癌病変から進展する場合もあります。
初期症状は、皮膚の一部に発赤やイボ状の隆起がみられることです。進行するとびらんや潰瘍を形成し、出血や角化性結節が生じるほか、腫瘍が硬くなることがあります。さらに進行すると、腫瘤から体液が浸出し、独特の悪臭が発生する場合もあります。多くの場合、自覚症状はありませんが、神経浸潤が起こると強い疼痛を伴うことがあります。
有棘細胞がんは早期発見で治癒の可能性が高まりますが、リンパ節への転移リスクもあるため、疑わしい症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。
有棘細胞がんが疑われる所見
- 表面がジュクジュクしている、かさぶた状態になっている
- 同じ場所にできものが繰り返し生じている
- 悪臭がする
- 顔面や手の甲などの日光(紫外線)を浴びやすい部位にできている
前癌病変について
赤みを帯びた皮膚がんの中には、有棘細胞がんやその類症が含まれます。その代表的なものが「日光角化症」と「Bowen(ボーエン)病」です。どちらも表皮を構成する角化細胞から発生するがんであり、前癌病変と呼ばれます。
これらの病変を放置すると、有棘細胞がんに移行する可能性があるため、早期の診断と適切な治療が必要です。
日光角化症
日光角化症は「老人性角化症」とも呼ばれ、日光(紫外線)を長期間浴びることで発生する前癌病変です。高齢者に多くみられ、特に頭皮や顔、手の甲など、日光が浴びやすい部位に生じやすい特徴があります。また、繰り返し日焼けをしている方や、色白で皮膚が赤くなりやすい方に発生しやすい傾向があります。
日光角化症は症状によっていくつかの病型に分類されます。最も多いのは紅斑型で、これは数ミリから2センチ程度の赤いシミのようなカサカサした状態が特徴です。症状は目立たず、境界が不明瞭で、数ヶ月以上治らない場合もあります。その他の病型として、褐色のシミのようなやや隆起を伴う色素沈着型や、イボのような疣状(ゆうじょう)型があります。
日光角化症が疑われる場合には、ダーモスコピー検査(拡大鏡検査)や病理検査で診断が行われます。治療法は症状に応じて選択され、外科的切除や液体窒素を使用した凍結療法、免疫調整薬(イミキモド)による外用療法などがあります、
Bowen(ボーエン)病
ボーエン病は、皮膚の最外層である表皮に発生する前癌病変です。顔面のような露出した部位だけでなく、以下のような服で隠れる部位にも発生しやすい特徴があります。
- お腹
- 背中
- 体幹部
- 陰部
- 手足
ボーエン病は60歳以上の高齢者に多くみられ、湿疹や日光角化症と類似した外見を持ちます。痛みやかゆみといった自覚症状はなく、赤茶色でザラザラした平坦な隆起として現れます。この隆起は徐々に大きくなり、5~10センチ程度の大きさに達することもあります。正常な皮膚との境界は明瞭ですが、形状は不規則です。
ボーエン病は表皮内にとどまるがんであり、この段階では転移は起こりません。しかし、表皮を越えて真皮層に浸潤すると、有棘細胞がんへ移行する可能性があります。
発生原因としては、ウイルス性皮膚疾患や外傷後の傷あとが挙げられます。まれに多発することがあり、その場合は井戸水の長期摂取によるヒ素中毒が原因とされることがあります。また、陰部に発生した場合は、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因とされています。
ボーエン病が疑われる場合には、ダーモスコピー検査や病理検査が行われます。初期段階であれば外科的切除により完治が期待できますが、放置すると深部への進行や悪性度の上昇のリスクが高まります。そのため、疑わしい症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。
悪性黒色腫(メラノーマ)
悪性黒色腫は、一見ほくろに似た見た目をしている代表的な皮膚がんです。いびつな形状で、黒色の隆起として現れるのが特徴です。悪性黒色腫は、メラニン色素を生成する細胞(メラノサイト)ががん化することで発生し、皮膚がんの中でも悪性度が高い傾向にあります。そのため、他の皮膚がんとは異なり、特別な対応が必要な場合があります。
発症率には人種差があり、白人に比べて日本人では比較的まれで、10万人あたり1〜2人程度とされています。紫外線の曝露が多い顔や手足の末端部に発生しやすく、日本人では以下の部位に多くみられます。
- 足の裏
- 手のひら
- 爪
ほくろ(母斑細胞)から悪性黒色腫が発展することもあり、「ほくろのがん」とも呼ばれることがあります。大きなほくろができる、または急にほくろができるといった変化がみられる場合は、悪性黒色腫の可能性があります。悪性黒色腫は、小さな段階でもリンパ管や血管を通じて全身に転移するリスクがあるため、早期発見が重要です。
悪性黒色腫が疑われる所見
- 形が左右非対称
- 皮膚との境界や輪郭が不明瞭
- 色がまだらで濃淡が不均一
- サイズが6ミリ以上
- サイズや形状、色調などが急に変化している
皮膚がんは放置せず、早期からの治療を
表皮にとどまり、転移がみられない初期の皮膚がんであれば、手術による完全摘出で高い確率で完治が期待できます。しかし、皮膚がんが進行するとリンパ節や内臓への転移、皮膚深部への浸潤リスクが高まり、広範囲の手術や抗がん剤治療が必要になる場合があります。皮膚がんの特徴を理解し、疑いがある場合は早期に医療機関を受診し、適切な治療を受けることが重要です。
当院では、患者様の状態や検査結果に基づき、治療方法について詳しくご説明し、十分な同意を得たうえで治療を行なっています。
手術の際は、切除した腫瘍が完全に除去できているかを確認し、必要に応じて皮膚欠損の修復を行います。修復方法にはさまざまな選択肢があり、欠損が小範囲の場合は縫合閉鎖や皮弁術(皮膚の血流を保ちながら移植する方法)を行います。欠損が広範囲の場合は植皮術を実施します。このように、腫瘍の切除範囲や患者様の希望を考慮して、適切な手術方法を選択します。
「できもの」や気になる症状がある方、また皮膚がんではないかと不安に感じている方は、当院までご相談ください。
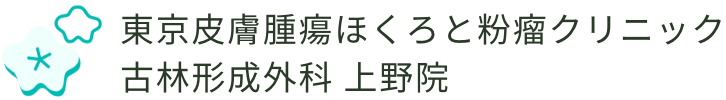

 アクセス
アクセス


