粉瘤の治し方 |自分で潰すのは危険!正しい治療法を解説!

東京都台東区上野の「東京皮膚腫瘍ほくろと粉瘤クリニック 古林形成外科上野院」です。当院では、日帰り手術による粉瘤の治療を行っています。
本記事では、粉瘤の治し方(正しい治療法)や自己処置によるリスクなどについて解説します。ぜひご参考ください。
粉瘤の基本知識

粉瘤(ふんりゅう)は、皮下に発生する良性腫瘍の中でも最も代表的な疾患の一つです。ここでは、粉瘤の基本的な特徴と発生のメカニズムについて解説します。
粉瘤の特徴
粉瘤は、「アテローム」や「表皮嚢腫(ひょうひのうしゅ)」とも呼ばれる良性の腫瘍で皮膚の下に袋状の構造(嚢腫)が形成され、その内部に皮脂や角質などの老廃物がたまることで形成されます。
体のどこにでも発生する可能性がありますが、特に顔、首、背中、耳の後ろなどによく見られます。
初期の粉瘤は、数ミリ程度の小さなふくらみとして現れ、痛みやかゆみなどの自覚症状はほとんどなく、触れると小さなしこりのように感じられます。この段階では大きな問題になることは少ないものの、放置すると徐々にサイズが大きくなる可能性があります。
粉瘤が進行すると、皮膚が目立つほどに盛り上がり、触れたときに独特の悪臭を放つこともあります。さらに、細菌感染を起こして炎症を伴うと、化膿や発熱、強い痛みを引き起こすことがあり、その場合は早急な処置が必要です。
粉瘤の発生メカニズム
粉瘤は、本来は皮膚の表面にあるべき表皮の一部が、外傷や摩擦などの刺激によって皮膚の内部に入り込むことをきっかけに、袋状の構造(嚢腫)を形成することで発生します。この袋の内部に、角質や皮脂などの老廃物が蓄積されていき、やがて皮下でしこりとして成長していくのが特徴です。
その発症原因は現時点では明確には解明されていませんが、ウイルス感染や皮膚の外傷が発症のきっかけになることがあります。また、体質的に粉瘤ができやすい方もおられ、複数の粉瘤が同時に、あるいは時間をおいて繰り返し発生するケースもあります。
粉瘤を自分で潰すのは危険

粉瘤の症状に気づいた患者様の中には、自分で潰して中の内容物を押し出そうとする方もいらっしゃいます。しかし、粉瘤に対する自己処置は危険であり、様々なリスクを伴います。ここでは、自分で粉瘤を潰すことで生じるリスクについて解説します。
細菌感染のリスク
自己処置で粉瘤を無理に潰すと、皮膚から細菌が侵入し、感染を引き起こす恐れがあります。感染が起こると、患部が赤く腫れて熱を持ち、激しい痛みや発熱を伴うこともあります。
また、炎症が進行した粉瘤は切開排膿などの追加処置が必要になることも多く、治療が長期化する傾向にあります。
再発のリスク
粉瘤は、皮膚の下に袋状の構造(被膜)が形成され、そこに老廃物がたまることで発生します。中身の老廃物だけを押し出しても、被膜を完全に除去しない限り再発のリスクが高いとされています。さらに、無理に潰すことで組織が癒着してしまい、治療が難しくなることもあります。
傷跡が残るリスク
自分で無理に粉瘤を押しつぶすと、炎症や細菌感染を引き起こし、皮膚に強いダメージを与えるおそれがあります。その結果、治療後に傷跡が目立つ可能性があります。
特に顔や首などの目立つ部位では、見た目の問題にもつながるため注意が必要です。
粉瘤の治療

粉瘤は自然に治ることはなく、放置するとサイズが大きくなり、治療後に傷跡が残るリスクや、感染や炎症などのリスクが高まるため、早期の治療が重要です。ここでは、粉瘤の治療法と適切な診療科について解説します。
粉瘤の治療法
粉瘤は、皮膚の下に袋状の構造(被膜)が形成される良性の腫瘍です。この被膜を手術で完全に取り除かない限り、自然に治ることはなく、再発を繰り返す可能性があります。そのため、根本的な治療には外科的な摘出手術が必要です。
粉瘤の手術には、主に「くり抜き法」と「切開法」の2種類があります。いずれも局所麻酔で行われ、基本的には日帰りでの手術が可能です。手術はもちろん、検査、診断、病理検査などの診療は、すべて健康保険が適用されます。
粉瘤の診療科
粉瘤の治療を受ける際には、形成外科や皮膚科が適切な診療科となります。
形成外科は、体の表面に生じた病変を外科的な手術で治療することを専門とする診療科であり、皮膚科は、全身の皮膚に関する病気を診察・治療する診療科です。
どちらを受診すべきか迷われる方も多いですが、粉瘤を根本的に治療するには、外科的な摘出手術が必要となるため、当院では形成外科の受診を推奨しています。
まとめ

粉瘤は皮下に発生する代表的な良性腫瘍の一つであり、自然に治癒することはありません。粉瘤の症状に気づいた患者様の中には、自分で潰して中の内容物を押し出そうとされる方もいますが、自己処置は感染や再発、傷跡が残るなどのリスクを伴い危険です。
根本的な治療を行うためには、原因となる袋状の構造(被膜)を手術で完全に摘出する必要があり、外科的な処置が不可欠です。粉瘤の手術は皮膚科でも対応可能ですが、傷跡の仕上がりや再発予防の観点からは、外科的処置を専門とする形成外科での診療が推奨されます。
粉瘤の症状に気づいた際は、早めに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。
粉瘤の治療は当院までご相談ください

東京都台東区上野の「東京皮膚腫瘍ほくろと粉瘤クリニック 古林形成外科上野院」では、粉瘤の治療を日帰り手術で行っています。
当院では、皮膚領域を専門とする日本形成外科学会認定の形成外科専門医が診療を担当しています。患者さま一人ひとりの状態に合わせ、豊富な知識と経験に基づいた治療をご提供いたします。
粉瘤でお困りの方は、当院までお気軽にご相談ください。
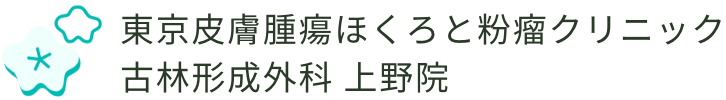

 アクセス
アクセス



