良性腫瘍とは
皮膚や皮下組織の細胞が増殖すると、腫瘍が発生することがあります。これを医学的には「皮膚腫瘍」と呼び、一般的には「できもの」や「しこり」として認識されています。
皮膚腫瘍は、その性質により「良性」と「悪性」の2種類に分類されます。良性腫瘍は成長が限定的で、腫瘍細胞が体の他の部位に転移しないことが特徴です。一方、腫瘍の成長が持続し、周囲の正常な組織に影響を与える場合は、悪性腫瘍である可能性があり、一般にこれを「がん」と呼びます。悪性腫瘍は、周囲の組織に浸潤し、体内の他の部位に転移するリスクがあります。
これらの腫瘍は形状が多岐にわたります。たとえば、隆起しているものや平らなものがあり、色も黒色や褐色などさまざまです。また、皮膚腫瘍には、生まれつき見られる先天性のものもあれば、後天的に発生するものも存在します。
皮膚腫瘍の多くは良性であり、放置しても命に関わる重大な問題を引き起こすことはほとんどありません。しかし、時間の経過とともに腫瘍が大きくなることで、外見上の変化や機能的な問題を生じることがあります。さらに、稀ではありますが、良性腫瘍が悪性に変化するケースも報告されています。
皮膚に異常を感じた場合は、できるだけ早く医療機関を受診することが大切です。多くの場合、ダーモスコピー検査により診断が可能ですが、確定診断には皮膚生検による組織検査が必要となることがあります。
表皮母斑(ひょうひぼはん)
表皮母斑は、出生時または生後2~3か月頃に発生する褐色でザラザラとした質感を持つ母斑(あざ)を伴う腫瘍です。この状態は、表皮が異常に形成されることで起こります。以下のような部位に帯状で現れることが多いのが特徴です。
- 顔
- 首
- 体
- 四肢
新生児約1,000人に1人の割合で発生するとされ、明確な原因は現在のところ解明されていません。
表皮母斑は自然に消えることはなく、成長とともに徐々に大きくなる傾向があります。治療の主な選択肢として、外科的切除が基本であり、以下の方法が挙げられます。
- 手術による切除
- 高周波メス
- 超音波メス
- 炭酸ガスレーザー
これらの治療法では、隆起した表皮部分を除去します。処置後の皮膚は軽い擦り傷のような状態となり、軟膏を用いてケアを行います。傷の治癒には約1週間かかり、その後もしばらくは赤みが残る場合がありますが、時間とともに目立たなくなります。
粉瘤(アテローム)
粉瘤は良性の皮下腫瘍の一つで、「表皮嚢腫(ひょうひのうしゅ)」とも呼ばれます。皮膚の上皮成分が皮下に入り込み、袋状の組織を形成することで発生します。この袋状組織の中に角質や皮脂などの老廃物が蓄積されることで、粉瘤が形成されます。体のあらゆる部位に発生する可能性がありますが、特に顔、首、背中、耳の後ろなどに多く見られます。ウイルス感染、外傷、体質などが発症要因と考えられていますが、正確な原因は解明されていません。
初期段階では数ミリ程度の小さな隆起として現れ、外見上はニキビやしこりに似ています。サイズが小さい段階ではあまり目立ちませんが、時間とともに徐々に大きくなります。また、悪臭を放つ場合や、細菌感染や圧迫により炎症を引き起こすこともあります。
粉瘤はニキビや吹き出物と誤解されることがありますが、自然に治ることはありません。そのため、治療には手術による適切な処置が必要です。自分で内容物を取り除こうとすると、袋が破れ、炎症を起こす恐れがあります。また、脂肪組織内に内容物が散らばり、症状が慢性化する原因にもなります。自己処置は避け、早めに医療機関を受診してください。
皮様嚢腫(ひようのうしゅ)
皮様嚢腫は、目や鼻の周囲、耳の後ろ、口腔底など、顔面領域に好発する円形の良性腫瘍です。
全身のどこにでも発生する可能性がありますが、皮膚で見られるものは後腹膜や卵巣に生じる腫瘍とは異なり、皮膚成分のみで構成されています。このタイプは「皮下皮様嚢腫」と呼ばれて区別されます。発見される時期はさまざまで、出生直後に見つかる場合もあれば、ゆっくり成長する性質のため、幼少期以降に初めて気付かれることも珍しくありません。
皮様嚢腫は無痛性で半球状に隆起し、皮膚との癒着はありませんが、骨膜と癒着しているケースが多く、可動性が悪いのが特徴です。また、腫瘍によって圧迫された骨が薄くなり、陥凹変形を引き起こすことがあります。内容物には皮脂に富む角質や毛髪が含まれており、チーズやクリームのような質感を持つのが特徴です。
治療は原則として手術による摘出が行われます。皮下に限局している場合は単純摘出で再発のリスクも低い傾向にあります。しかし、腫瘍が脳内に及ぶ可能性がある場合には、CTやMRI検査を実施し、適切な手術方法を慎重に選択する必要があります。一部の症例では、開頭手術が必要になる場合もあります。
稗粒腫(はいりゅうしゅ)
稗粒腫は、原発性と続発性の2種類に分類されます。原発性は主に小児や思春期以降の女性の顔面に発症し、続発性は水疱症、熱傷瘢痕、放射線皮膚炎などに続いて現れることが特徴です。いずれのタイプも白色がかった1~3ミリの半球状の丘疹として現れます。特に下まぶたの表皮に出現しやすく、内部に角質を含んでいます。
稗粒腫は自然に消失することも多いため、必ずしも治療が必要ではありません。しかし、若い女性に発生しやすいことから、美容上の懸念で治療を希望される方も多くいます。
治療は、皮内注射針を用いて皮膚を微小切開し、内容物を摘出する方法があります。また、炭酸ガスレーザーで穴を開け、真皮上層まで到達し、嚢腫壁ごと蒸散させる方法もあります。
汗管腫(かんかんしゅ)
汗管腫は、主に下まぶたに多くみられる1〜2ミリ程度の多発性の小結節です。ブツブツとした盛り上がりが点在しているのが特徴で、中には癒合して発生するケースもあります。下まぶた以外にも、頬部、前胸部、腹部、外陰部などに発生することがあります。
この疾患は、汗を分泌するエクリン汗腺の細胞が異常に増殖することで引き起こされます。目立った症状はないものの、自然治癒は期待できません。また、顔面に発生する場合には美容上の懸念から治療を希望されることが多いです。治療方法としては、主に炭酸ガスレーザーなどが検討されます。
脂腺母斑(しせんぼはん)
脂腺母斑は、先天性の皮膚奇形の一つです。主に頭部や顔面に発生しやすく、多くの場合、黄色いあざのような見た目をしています。初期段階では皮膚とほぼ同じ色のため、見分けがつきにくいことがあります。頭部に発生する場合、脱毛斑のように見えることが特徴です。表面はザラザラしていることが多い一方で、平坦な場合もあります。
脂腺母斑の症状は年齢とともに進行し、主に3つの臨床期に分類されます。
出生時は円形脱毛のような母斑を生じ、蒼白から黄色調の色をしています(第1期)。年齢を重ねるとともに隆起しはじめ、少しずつあざがイボ状となり、褐色味を帯びていきます(第2期)。思春期には症状が顕著になり、30歳以降ではまれに腫瘍化や悪性化のリスクが生じます(第3期)。
進行する性質があるため、症状が目立ち始める小中学生以降に外科的切除を検討することが一般的です。
母斑を完全に切除することで、続発性の腫瘍の発生リスクを低減できます。しかし、切除縫合部では線状瘢痕が残る可能性があり、頭部の場合は脱毛が生じることもあります。また、植皮が必要な場合、植皮部に色素沈着や拘縮が生じたり、採皮部に瘢痕が残ったりすることがあります。
石灰化上皮腫(毛母腫)
石灰化上皮腫は、毛穴の深部にある毛を形成する毛母(もうぼ)細胞が石灰化することで発生する腫瘍です。主に顔、首、腕などに0.5~3センチ程度の硬いしこりとして現れるのが特徴です。見た目は水疱(水ぶくれ)に似ており、腫瘍が大きくなると、皮膚の薄い部分では黄白色や青黒い色に透けて見えることがあります。
正確な発症メカニズムは分かっていませんが、子どもや女性に多く見られます。丸い形状をしているため、粉瘤や脂肪腫と間違われることもあります。
石灰化上皮腫は通常、単発で発症しますが、多発性の場合、「筋緊張性ジストロフィー」を合併するケースが報告されています。多くの場合、目立った症状はありませんが、しこりを押すと痛みやかゆみを感じることがあります。また、細菌感染や異物反応が起こると、強い痛みやかゆみを伴い、皮膚に穴が開く可能性もあります。このような症状が現れた場合、早急な手術による除去が推奨されます。
ほくろ
ほくろは良性腫瘍の一種で、メラニン色素を生成するメラノサイトが表皮に集まることで形成されます。外観は多様で、平坦なものや隆起したもの、茶色から黒色までさまざまな色調があります。形状も円形や楕円形などさまざまで、人によってはその方の特徴や魅力となる場合もあります。しかし、まれに悪性化しているものが含まれている可能性があるため、異常が見られる場合は注意が必要です。
ほくろと皮膚がんを見分けることは難しいため、患者様の症状や状況を丁寧に確認したうえで、適切な検査を実施します。主に使用されるのはダーモスコピーという皮膚拡大鏡で、悪性の可能性があるかを判断します。検査で悪性の可能性が高いと診断された場合には、手術による切除と病理検査を行い、最終的な診断を確定します。
ほくろに変化が見られ、皮膚がんの特徴に似ている場合は、早めに医療機関を受診することが重要です。
扁平母斑(へんぺいぼはん)
扁平母斑は、平らな茶色のあざのような形状をしており、「カフェオレ斑」とも呼ばれます。
表皮の肥厚や表皮突起が認められ、メラニンが皮膚の浅い部分に増加することで形成されます。ほくろとは異なり、皮膚表面が盛り上がることがないのが特徴です。多くの場合、生まれつきまたは幼少期に現れますが、思春期に発症する遅発性のケースもあります。
扁平母斑は先天性・遅発性いずれも良性であり、悪性化のリスクは極めて低いです。そのため、治療は主に美容的な目的で行われます。治療法としては、レーザー治療が標準的なアプローチとして用いられています。
神経鞘腫(しんけいしょうしゅ)
神経鞘腫は、神経を覆う神経鞘(神経のさや)に由来する良性腫瘍です。末梢神経のシュワン細胞から発生するため、「シュワン細胞腫」とも呼ばれます。多くは軟部組織に発生し、硬い球状の腫瘍として触れることができます。また、神経鞘だけでなく、脳や脊髄、消化管などにも発生する場合があります。
発生部位によって症状は異なり、皮下に生じた神経鞘腫では、圧迫時に痛みを感じることがあります。このような場合、外科的介入が検討されます。特に大きな神経に関わる腫瘍の場合、術後に神経障害が生じるリスクがあります。そのため、拡大鏡を使用し、腫瘍と正常な神経を注意深く剥離することで、神経障害の予防に努めます。
神経線維腫(しんけいせんいしゅ)
神経線維腫は柔らかく、常色から淡い紅色をした腫瘍で、皮膚表面や皮下組織に発生します。大きさはさまざまで、多くの場合、思春期頃から少しずつ現れ始め、加齢とともに数が増加することがあります。単発性のものもありますが、多発性の場合、「神経線維腫症Ⅰ型(レックリングハウゼン病)」との関連が疑われます。
神経線維腫は痛みなどの自覚症状がなく、悪性化のリスクもほとんどありません。しかし、美容上の理由から摘出を希望される方が多くいらっしゃいます。治療法としては、外科的切除手術が一般的に行われています。
イボ
イボは、皮膚上に隆起した数ミリから数センチほどの小さなできものです。原因は加齢やウイルス感染などがあげられ、外見も種類もさまざまです。放っておくと肥大化し、治療が難しくなるケースもあります。また炎症を伴ったり、日常生活に支障をきたしたりすることもあるため、気になる症状があれば早めの受診が推奨されます。
主なイボの種類
イボ(尋常性疣贅:じんじょうせいゆうぜい)
尋常性疣贅は、イボの中で最も一般的な種類で、多様な形状をしています。原因としては、皮膚の傷口から「ヒトパピローマウイルス(HPV)」が感染することがあげられます。基本的に痛みやかゆみなどの症状がありません。しかし、放置するとイボが増加したり、他人に感染したりする恐れがあります。
水イボ(伝染性軟属腫:でんせんせいなんぞくしゅ)
水イボはポックスウイルスの感染によって発生するイボです。光沢のある小さなドーム状の形状をしているのが特徴です。主に6歳以下の子どもに多く発生し、胸や腹部、脇の下などの皮膚の薄い部分に好発します。サイズは数ミリ程度のものが多く、掻くことで内容物が皮膚に付着し、感染を引き起こす可能性があります。そのため、集団生活を送る子どもに発生した場合、早めに治療を受けることが重要です。
老人性イボ(脂漏性角化症:しろうせいかくかしょう)
老人性イボは、紫外線による肌の加齢性変化が原因で発生するとされるイボです。主に円形状の隆起として現れます。一般的に中高年に多いとされていますが、20代での発症も珍しくありません。色は茶色や黒褐色などで、顔や頭部、胸などによくみられます。年齢とともに数が増える傾向があり、平坦なシミから隆起して老人性イボに変化することもあります。
首イボ(アクロコルドン)
首イボとは、非感染性の脂漏性角化症(老人性イボ)の一種です。首周りや脇の下、鼠径部などの皮膚の柔らかい部分に発生すると、有茎性に隆起した小さなイボとして現れるケースがあります。首イボは健康に深刻な問題を引き起こすわけではありませんが、衣類との接触でねじれ、痛みや炎症を引き起こすことがあります。
皮膚線維腫
皮膚線維腫とは、成人女性の腕や足などに好発する、数ミリから数センチ程度の大きさの良性腫瘍です。色は肌色から茶色で、皮膚表面が隆起しており、皮下にやや硬いしこりとして現れます。痛みやかゆみなどの目立った症状はありません。しかし、患部を圧迫すると痛みが現れ、発生部位によっては衣類との摩擦で不快感を覚えることがあります。原因は完全にわかっておらず、虫刺されや小さな傷、遺伝的要因が関係していると考えられています。
皮膚線維腫は、発生してもほとんどの場合問題がありません。しかし、サイズが大きい場合や増加傾向がある腫瘍には注意が必要です。まれにDFSP(隆起性皮膚線維肉腫)という悪性腫瘍の可能性があるため、異常が現れた際には鑑別のために病理検査が行われます。
肥厚性瘢痕(ひこうせいはんこん)
肥厚性瘢痕は、何らかの原因で傷の治癒が遅れ、傷あとが硬く盛り上がった状態を指します。外傷や熱傷、手術によって皮膚に創傷が生じた場合、通常は治癒が進むにつれて平らな瘢痕になります。しかし、傷が深かったり広範囲であったりすると、肥厚性瘢痕が生じることがあります。一見するとケロイドに似ていますが、肥厚性瘢痕は異なる疾患です。
肥厚性瘢痕の特徴
- 全身に発生する
- 受傷範囲を超えずに瘢痕が現れる
- 受傷部周辺に炎症が現れない
- 半年から数年で扁平化する
特にケロイドとの鑑別をするためには、(2)と(3)がポイントとなります。
治療は保存療法が行われ、内服薬の使用、副腎皮質ステロイド含有テープの貼付、圧迫療法などが主な選択肢です。その他にも外科的切除を行う場合もあり、症状の程度や経過に応じて保存療法と併用して治療を進めます。
ケロイド
ケロイドとは、傷あとが異常に盛り上がり、痛みやかゆみを伴う状態のことです。通常の傷の治癒過程で炎症反応が過剰に続き、線維成分が異常増殖することが原因で生じます。主な症状は、以下のとおりです。
- 患部とその周囲の腫れ・盛り上がり
- 痛み
- かゆみ
- 引きつれ感
前胸部や肩まわり、上腕、耳などに好発する一方で、手掌や足底、顔面などには生じにくいとされています。見た目も変化するため、ケロイドを気にする方も多くみられます。ケロイドは自然治癒せず、むしろ元の傷を超えて広がるのが特徴です。
ケロイドの発症には、個人の体質が大きく関与しているといわれています。症状の程度は個人差があり、同じような傷でもケロイドを形成することもあれば、通常の傷あとで済むこともあります。ケロイドの原因はさまざまで、手術や外傷などだけでなくBCG接種痕やピアス、さらにはニキビや虫刺されのような小さな傷でも発症することがあります。
脂肪腫(リポーマ)
脂肪腫(リポーマ)とは、皮膚の下に発生する良性腫瘍です。軟部組織に生じる良性腫瘍の中で、最も多くみられる腫瘍の1つです。発生部位は全身に及び、背部や肩、頚部(特に後頚部)に多く、四肢にも現れることがあります。
脂肪腫は痛みやかゆみなどの症状を伴わず、皮膚表面がドーム状に隆起し、柔らかいしこりとして感じられます。大きさはさまざまで、わずか数ミリのものから10センチを超えるものまであります。放置すると徐々に成長し、目立ちやすくなります。脂肪腫の正確な原因は不明ですが、肥満や糖尿病、遺伝的要因などが関連していると考えられています。
脂肪腫は自然治癒が期待できず、薬物療法での治療も期待できません。そして内容物が液体ではないため、注射による吸引も不可能です。完治には外科的な摘出が必要となります。
脂肪腫は、大きくなると手術の難易度が上がり、それに伴い費用面での負担も増加します。脂肪腫は良性腫瘍ですが、その外見が悪性腫瘍と類似している場合があります。そのため、小さなしこりであっても、発見した際には速やかに専門医の診察を受けることが重要です。
皮膚平滑筋腫(ひふへいかつきんしゅ)
皮膚平滑筋腫とは、皮膚の中にある平滑筋組織から発生する良性腫瘍です。一般的に、皮膚の表面にしこりや腫瘤などが現れるのが特徴です。しこりや腫瘤は硬く、押したときに圧痛を伴いやすく、皮膚の色や質感が変化することがあります。皮膚平滑筋腫は、以下のように分類されています。
- 立毛筋由来平滑筋腫:体幹や四肢に小結節として現れ、単発性と多発性の2種類がある
- 陰部平滑筋腫:大陰唇、会陰、陰茎、乳頭、乳輪部などの部位に発生する
- 血管平滑筋由来平滑筋腫:下肢に多く生じ、痛みのあるものとないものがある
皮膚平滑筋腫の治療は、症状や腫瘍の大きさなど、患者ごとの状況に応じて決定されます。外科的処置を行う場合、良性腫瘍である特性を考慮し、辺縁切除による摘出が一般的です。多発性腫瘍の場合、疼痛を伴う箇所を優先的に切除し、症状緩和を重視します。腫瘍が小さい、または症状が現れていない場合は、経過観察となることもあります。
外骨腫(がいこつしゅ)
外骨腫とは、原発性の骨腫瘍の中で最も多いとされている良性腫瘍です。骨幹端部(骨の端)にツノのような突起として現れる骨腫瘍であり、表面が軟骨で覆われていることから、骨軟骨腫(こつなんこつしゅ)とも呼ばれています。形成外科領域では、前額部(おでこ)や頭蓋、爪下などに好発します。
前額部や頭蓋の外骨腫は痛みを伴わないことが多いですが、美容的な懸念から切除を望む患者様も多くいます。この腫瘍の治療では、主に手術による摘出が選択されます。局所麻酔下で行われる手術では、ツチとノミを使用して腫瘍を慎重に取り除きます。摘出後の組織は、病理検査を行います。手術後は、形成外科的な技術によって創部を細かく縫合し、目立たないような仕上がりを目指します。
毛細血管拡張性肉芽(もうさいけっかんかくちょうせいにくげ)
毛細血管拡張性肉芽とは、皮膚の微細な傷や細菌感染がきっかけとなり、毛細血管が拡張・増殖することで発生する良性腫瘍です。通常、直径5ミリから2センチほどの大きさで、発生から2〜3週間で成長は止まります。鮮やかな赤色や暗赤色をしており、柔らかい有茎性の盛り上がりとして発生します。痛みやかゆみなどはありませんが、毛細血管が豊富なのでわずかな刺激でも出血しやすく、潰瘍形成のリスクがあります。止血が困難で、繰り返し出血するため、生活に支障をきたすことも珍しくありません。
毛細血管拡張性肉芽は、年齢によって好発部位が異なり、小児では顔面に、成人では手指や四肢、体幹に多くみられます。
また、妊娠中に発生頻度が高くなることから、女性ホルモン(エストロゲン)と関連があると推測されています。
小型の腫瘍の治療では、ステロイド軟膏の塗布によって消退することもあります。そのほかの治療としては、炭酸ガスレーザー、電気焼灼、外科的切除などが選択されます。
グロムス腫瘍(ぐろむすしゅよう)
グロムス腫瘍とは、比較的珍しい血管系の腫瘍です。紫青色または赤色の小さな腫れとして現れ、主に手足に発生し、特に指の爪の下によくみられます(指の腹側にできることもある)。激しい痛みを引き起こしやすく、拍動痛を伴うこともあります。また、寒冷刺激や圧迫によって症状が悪化する傾向があります。
腫瘍が小さいものや爪の下にあるものは、見た目だけでの診断が困難なケースがあります。そのような場合は、MRI検査によって診断します。治療は主に外科的摘出を行います。爪下の腫瘍を摘出する際は、爪全体を除去し、爪床を縦に切開してアプローチします。爪床は薄く、繊細な組織のため、細心の注意を払いながら手術を進めていきます。
ガングリオン
ガングリオンとは、手首の関節付近にみられやすい腫瘤のことです。大きさはさまざまで、米粒ほどの小さなものからピンポン玉に匹敵するサイズまで存在し、柔らかいものから硬いものまで多岐にわたります。手首の関節には「関節包(関節を包んでいる組織)」があり、その中には潤滑油の役割がある滑液(かつえき)が満たされています。この滑液が何らかの理由で外部へ漏出し、皮下で袋状の腫瘤を形成することで、ガングリオンが生じます。
ガングリオンは手首の関節付近に多くみられますが、指の付け根の腱鞘に発生するケースもあります。多くの場合、神経の圧迫によって痛みを感じることがあるものの、そこまで強いわけではありません。治療には保存的な方法と外科的な摘出があります。注射による内容物の吸引も行われますが、繰り返し再発する場合は手術による治療が推奨されます。
毛細血管奇形(もうさいけっかんきけい)
毛細血管奇形は先天性疾患で、「赤あざ」として知られる病変の代表的な一種です。かつては単純性血管腫、ポートワイン血管腫、火炎状母斑などの名称で呼ばれていました。
毛細血管は動脈と静脈をつなぐ細い血管で、体全体の皮膚に広がっています。この毛細血管が異常に増殖・集合したものが毛細血管奇形です。症状の範囲は軽微なものから、顔面、四肢、体幹の広範囲にわたるものまでさまざまです。自然治癒は期待できず、症状が緩やかに進行し、年齢とともに色が濃くなることがあります。特に中年期以降には暗赤色に変化し、結節や隆起性病変が生じる場合もあります。
治療は、症状や範囲に応じてレーザー療法や手術が検討されます。
静脈奇形(じょうみゃくきけい)
静脈奇形とは、静脈が拡張・腫瘤化したもので、大小さまざまな血管腔が皮下や筋肉内に増える血液貯留性の病変です。体表面から青く透けて見えることがあり、その大きさや深さ、部位はそれぞれ異なります。症状としては起床時に痛みが出るほか、手足に発生している場合は下ろす際に血液量が増え、血管が膨らみます。血管の膨らみによって静脈石に触れたり、痛みを生じたりすることもあります。
先天性疾患のため自然治癒は期待できず、年齢とともに大きくなります。女性の場合、妊娠時や閉経後のタイミングで大きくなる傾向があります。
治療は症例に応じて異なり、MRIや超音波などの検査によって適切な方法を選択します。代表的な治療法としては、手術や特殊な薬を使用し、病変を小さくする硬化療法などがあげられます。
動静脈奇形(どうじょうみゃくきけい)
動静脈奇形とは、部分的な動脈と静脈の形成異常によって、腫瘤や組織が肥大化する血管性病変です。正常な血管構造(動脈⇒毛細血管⇒静脈)を持たず、動脈と静脈が直接つながっているため、血流が異常に速くなる特徴があります。そして病変内では、拡張・蛇行した異常血管が増えている状態です。
動静脈奇形の多くは進行性であり、初期症状として赤あざや拍動性のコブが現れます。病変が進行してサイズが大きくなると、痛みや出血などの症状を伴います。また、過剰な血流は心臓に負担をかけ、心機能に悪影響を与える可能性もあります。
完治を目指すには、手術による完全切除が選択されますが、大きな病変の場合、手術中の大量出血のリスクがあります。そのため、術前に栄養血管を詰める動脈塞栓術が必要になることがあります。
リンパ管奇形(リンパ管腫)
リンパ管奇形は、広義的には血管奇形の一種とされている病変です。従来はリンパ管腫と呼ばれており、拡張したリンパ管の大きさによって以下の種類に分かれているとされています。
- 嚢胞状
- 海綿状
- 単純性
- 限局性
この性質上、血管ではなくリンパ管に発生する疾患です。多くは先天性で、胎児期のリンパ管の形成過程で何かしらの異常が生じることが原因とされていますが、詳細はわかっていません。
リンパ管奇形は、首や脇の下に好発し、風邪を引いた際に熱発や腫脹、痛みなどの炎症症状が現れることがあります。首に発生した場合、気道が圧迫されて呼吸困難を引き起こし、時に重篤な呼吸管理を要することもあります。一方で、無症状のケースもあり、そういった場合は定期的な経過観察を行います。
治療としては、外科的切除の他に、リンパ管をつまらせる硬化療法、抗がん剤による治療、インターフェロン療法、ステロイド療法、レーザー焼灼法などが行われます。
乳児血管腫(にゅうじけっかんしゅ)・先天性血管腫(せんてんせいけっかんしゅ)
乳児血管腫とは、乳幼児にみられる血管性腫瘍で最も頻度が高い病変です。鮮紅色の斑点として現れ、徐々に皮下組織で増殖します。イチゴのような赤く隆起のある形状から、イチゴ状血管腫と呼ぶこともあります。多くの場合、生後数日から数週間以内に発生します。
血管は「内膜・中膜・外膜」の3層構造になっており、乳児血管腫は内膜を作る細胞(血管内皮細胞)が異常増殖・自然退縮する腫瘍です。通常1歳頃まで成長を続け、その後徐々に退縮し、7歳前後には消失します。この腫瘍は、以下の3つのタイプに分類されます。
- 局面型(血管内細胞の増殖が皮膚表面のみに限局するタイプ)
- 腫瘤型(皮膚表面と深部どちらも増殖するタイプ)
- 皮下型(深部にのみ血管内皮細胞が増殖するタイプ)
乳児血管腫の多くは治療を必要とせず、自然に軽快しますが、大きな病変や腫瘤型の場合、出血、潰瘍、瘢痕、毛細血管拡張、変形、遮薇性弱視などの症状を引き起こす恐れがあります。
このような症状が現れた場合、必要に応じて治療を行います。治療法としては、内服治療や色素レーザー治療などがあげられます。
先天性血管腫は胎児期に発生し、そのタイミングで増殖のピークを迎える特殊な血管腫です。出生後すぐに退縮するものと、そうでないものがあります。先天性血管腫は乳児血管腫と比較して、発生頻度はまれです。
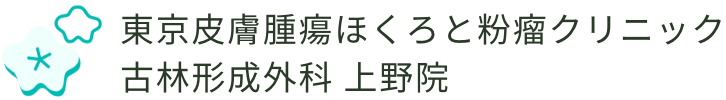

 アクセス
アクセス


