ほくろと皮膚がんの見分け方|注意すべき5つのポイントを解説!

東京都台東区上野の「東京皮膚腫瘍ほくろと粉瘤クリニック 古林形成外科上野院」です。当院では、日本形成外科学会認定の形成外科専門医によるほくろの治療を行っています。
この記事では、ほくろと皮膚がんの違いを見分けるためのポイントと、注意すべき症状について解説します。ぜひご参考ください。
ほくろと皮膚がんの見分け方

皮膚がんの中には、外見が良性のほくろと非常によく似ており、自己判断が難しいものがあります。代表的な皮膚がんとしては、悪性黒色腫(メラノーマ)、基底細胞がん、有棘細胞がん(扁平上皮がん)などが挙げられますが、特に注意が必要なのが「ほくろのがん」とも呼ばれる悪性黒色腫です。
悪性黒色腫は、メラニン色素を産生する色素細胞(メラノサイト)ががん化することで発生する悪性腫瘍であり、皮膚がんの中でも進行が早く、転移のリスクが高いのが特徴です。初期段階では、良性のほくろとの見た目の区別がつきにくいため、わずかな変化にいち早く気づき、早期に専門医を受診し、正確な診断と適切な治療を受けることが重要です。
悪性黒色腫を見分けるための「ABCDEルール」
国際的に広く推奨されている「ABCDEルール」は、ほくろが悪性である可能性を評価するための指標です。以下のいずれかに該当する場合は、悪性黒色腫の疑いがあるため、専門医の診察を受けることが推奨されます。
- A(Asymmetry):左右非対称な形をしている
- B(Border irregularity):輪郭が不明瞭で、周囲との境界があいまい
- C(color variegation):色にムラがあり、黒・茶・赤・白など複数の色が混在している
- D(Diameter):直径6ミリ以上
- E(Evolution):短期間で大きさ、形、色、表面の質感が変化している
悪性黒色腫以外の皮膚がんについて

皮膚がんにはさまざまな種類があり、進行が比較的緩やかなものから、早期に転移する悪性度の高いものまで、それぞれ異なる特徴を持っています。悪性黒色腫を除いた代表的な皮膚がんとしては、以下のようなものが挙げられます。
基底細胞がん
基底細胞がんは、表皮の最下層にある基底細胞や毛包の細胞ががん化することで発生すると考えられており、日本人に最も多くみられる皮膚がんです。特に高齢者の顔面(頬、まぶた、鼻の周囲など)や頭皮に好発します。
主な症状は、黒色または灰黒色の光沢を伴う小さな隆起で、数年かけてゆっくりと拡大し、やがて中央が陥没して潰瘍(えぐれた状態)を形成し、周囲が堤防状に盛り上がるのが特徴です。痛みやかゆみなどの自覚症状は少なく、気づかれにくい場合もあります。
転移することはまれですが、放置すると周囲の皮膚や深部の筋肉・骨へ浸潤する可能性があり、特に皮膚の薄い顔面では骨に達して変形をきたすこともあります。そのため、早期の診断と適切な治療が重要です。
有棘細胞がん(扁平上皮がん)
有棘細胞がんは、表皮の有棘層を構成する細胞ががん化して発生する皮膚がんで、「扁平上皮がん」とも呼ばれます。日本人では基底細胞がんに次いで多く、主に高齢者に発症します。鼻、耳、唇、まぶた、手の甲、頭皮など、紫外線にさらされやすい部位に好発します。
見た目の初期症状は、赤みを帯びた隆起やイボのようなしこりとして始まり、進行するとびらんや潰瘍へと変化します。かさぶたのような硬いしこり「角化性結節」ができ、滲出液や悪臭を伴うこともあります。初期には自覚症状が乏しいことが多いものの、神経に浸潤すると強い痛みが出る場合があります。
有棘細胞がんは、リンパ節や内臓への転移リスクがある皮膚がんのため、早期の発見と治療が極めて重要です。
関連ページ
ほくろと皮膚がんを見分けるための検査方法

ほくろと皮膚がんを正確に見分けるためには、専門的な検査が欠かせません。
まずは専門医による視診と触診が行われ、病変の形状、大きさ、色の濃さやムラ、盛り上がりの有無、出血やかさぶたがあるかなど、複数の項目を総合的に評価します。
その後、「ダーモスコピー(皮膚拡大鏡)」を使って、皮膚表面の色や模様のパターンを詳しく観察します。肉眼では見えにくい特徴も確認できるため、皮膚がんの可能性をより高い精度で判断できます。さらに、転移のリスクが高い皮膚がんが疑われる場合には、リンパ節や内臓への転移の有無を調べる目的で、超音波検査、CT、MRIなどの画像診断が行われる場合があります。
最終的な診断を確定するには、病変の一部または全体を切除して、病理組織検査を行う必要があります。
正確な診断には専門医の診察が不可欠

皮膚がんには、悪性黒色腫(メラノーマ)、基底細胞がん、有棘細胞がんなど、いくつかの種類があります。これらは、通常のほくろと見た目が似ていることも多いため、視覚的な情報だけで正確に区別することは困難です。
正確な診断のためには、専門医によるダーモスコピー検査などの評価が不可欠です。ほくろで気になる症状がある場合は、自己判断を避け、できるだけ早く専門医の診察を受けることが大切です。
ほくろの治療は当院までご相談ください

東京都台東区上野の「東京皮膚腫瘍ほくろと粉瘤クリニック古林形成外科上野院」では、日本形成外科学会認定の形成外科専門医が、皮膚領域における専門的な視点から、ほくろの診断と治療を行っています。
当院では、患者さま一人ひとりの症状やご希望に寄り添い、豊富な知識と経験に基づいた治療法をご提案いたします。治療においては、整容面にも十分配慮しながら、自然な仕上がりを重視した治療を提供しています。
ほくろに関する症状でお悩みの方は、当院までご相談ください。
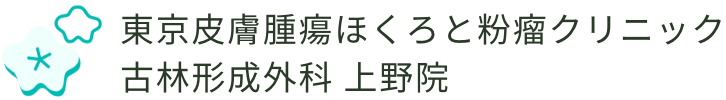

 アクセス
アクセス



