基底細胞がんの種類
結節潰瘍型
結節潰瘍型は、日本人に最も多く見られるタイプの基底細胞がんで、全体の約80%を占めるとされています。初期段階ではほくろに似た見た目をしていますが、次第に大きく隆起し、一部が潰瘍化して出血するケースもあります。
表在型
表在型は、全体的に平らな表面を持ち、まだら状に広がるのが特徴です。正常な皮膚との境界がはっきりせず、初期段階ではシミのように見えることがあります。
斑状強皮症型
斑状強皮症型は、表面に蝋状の光沢があり、毛細血管の拡張を伴うタイプの基底細胞がんです。この型は皮膚の深部へ浸潤する特徴があり、正常な皮膚との境界が不明瞭です。再発リスクが高いため、手術時には他のタイプより広範囲を切除する必要があります。
基底細胞がんの割合
日本人の基底細胞がんの発生率は0.002〜0.004%とされており、非常にまれな腫瘍です。一方で、白人では紫外線の影響を受けやすいことから、発生率が高い傾向があります。特にオーストラリアでは、基底細胞がんの患者は約1%に達するとされています。
基底細胞がんの原因
基底細胞がんの発症原因は明確にはわかっていません。しかし、紫外線、放射線、外傷、やけどなどが要因として関与していると考えられています。
基底細胞がんの検査
基底細胞がんの診断では、ダーモスコープを使用することがあります。ダーモスコピー検査で pigment network(色素ネットワーク) が確認された場合、悪性黒色腫や色素細胞母斑など、メラノサイト系腫瘍の可能性が考えられます。
Pigment networkが認められない場合、以下の所見の有無を確認します。
ulceration(潰瘍化)
large blue-gray ovoid nests(灰青色類円形大型胞巣)
multiple blue-gray globules(多発灰青色小球)
multiple leaf-like areas(多発葉状領域)
spoke wheel areas(車軸状領域)
arborizing vessels(樹枝状血管)
これらの所見のいずれかが認められた場合、90%以上の確率で基底細胞がんと診断されます。
上記の方法で診断が難しい場合、生検による診断を行う場合があります。基底細胞がんは転移の可能性が低いため、生検によって悪化するリスクは低くなっています。一方で、メラノーマの場合は転移の可能性があるため、生検を行う際には注意が必要です。
基底細胞がんの治療
外科的手術による治療
基底細胞がんの治療方法はいくつかありますが、最も推奨されているのが外科的手術です。外科手術では、基本的に病変の辺縁から3~5mm離して切除を行います。放射線療法や凍結療法、電気掻爬などと比較して、外科手術は再発率が低いことが確認されています。
たとえば、頭頸部で4cm以下の基底細胞がんの場合、外科的切除後4年間の再発率は0.7%であるのに対し、放射線治療では7.5%とされています。また、外科的切除は整容面でも優れており、放射線療法による正常組織へのダメージや潰瘍化のリスクがない点が利点です。
欧米では Mohs(モーズ)手術 が再発率を最小限に抑える方法として広く採用されています。しかし、日本では設備の制約や症例数の少なさから、ほとんど実施されていません。なお、通常の外科的切除とMohs手術の初回治療後の再発率に有意差が見られなかったという報告もあります。
外科的切除を行う際に重要なポイントは、腫瘍から何ミリ離して切除するか(切除マージン)です。欧米のデータでは、以下の数値が推奨されています。
低リスクの基底細胞がんには4mmの切除マージン
高リスクの基底細胞がんには5~10mmの切除マージン
2cm以下で境界が明瞭な基底細胞がんにおいては、切除マージンが3mmの場合、85%の症例で腫瘍残存が見られないとされています。切除マージンを4~5mmに拡大すると、95%の症例で完全切除が期待できます。
ただし、これらのデータは主に欧米のものに基づいています。発生率が低い日本では、切除マージンが2~3mmでも適切とする報告もあります。
放射線治療による治療
高齢者や、切除が難しい部位に発生した基底細胞がんの場合、放射線治療が行われることがあります。ただし、外科的手術と比較すると根治性は劣るとされています。
化学療法による治療
化学療法は、手術が難しい進行例で行われますが、初期治療として行われるケースはまれです。
外科的手術の治療例
下腹部の基底細胞がん
下腹部に1cm程度の基底細胞がんが確認されました。マージンを4mm取って拡大切除を行い、皮膚に余裕があったため単純縫合で閉創しました。

手術前

手術前
鼻の基底細胞がん(BCC)
手術前、鼻に基底細胞がんが確認されました。腫瘍から3mmのマージンを取って切除した後、皮弁(bilobed flap)を作成して腫瘍部を覆う処置を施しました。
皮膚欠損を単純縫合で閉じると鼻が変形する恐れがあるため、形成外科の技術を用いて皮弁を作成し、創部を閉じました。術後はやや鼻に歪みが見られますが、時間の経過とともに徐々に馴染んでいきます。

手術前

手術後
鼻根部の基底細胞がん(BCC)
手術前に鼻根部に基底細胞がんが確認されました。腫瘍からマージンを2mm取って腫瘍摘出術を行い、皮弁を作成して創部を覆いました。
単純縫合では歪みが顕著に現れる恐れがあるため、形成外科の技術を用いて皮弁を作成しました。術後にはやや歪みが見られることがありますが、時間の経過とともに徐々に改善していきます。
治療後の経過について
基底細胞がんの治療後の経過観察については、明確な頻度や期間に関するエビデンスはないとされています。しかし、多くの場合、術後半年ごとに診察を行い、その後の2~3年は年に1回の間隔で経過観察が行われることが一般的です。
基底細胞がんの患者は、他の皮膚がんや別の部位に新たな基底細胞がんが発生するリスクが高まる傾向があります。欧米のデータによれば、基底細胞がん患者の約20%が治療後1年以内に新たな基底細胞がんを発症し、5年以内では約40%の患者が新たな基底細胞がんを発症するとされています。また、基底細胞がん治療後、有棘細胞がんを発症するリスクが5~10%、メラノーマを発症するリスクが2~4倍に増加するとの報告もあります。
基底細胞がんは転移リスクが低い腫瘍であるため、通常はCTやMRIなどの画像検査は必要ありません。ただし、早期から適切な治療を行うためには、定期的な診察が重要です。新たな病変や異常を感じた場合は、早めに医療機関を受診してください。
参考文献
皮膚悪性腫瘍ガイドライン第3版 基底細胞癌ガイドライン2021
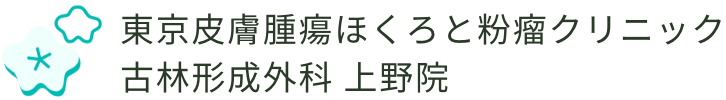

 アクセス
アクセス










